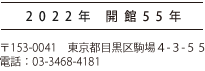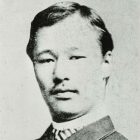教科書のなかの文学/教室のそとの文学Ⅲ──森鷗外「舞姫」とその時代
6月28日(土)―9月6日(土) 
| 開館時間 | 午前9時30分~午後4時30分(入館は午後4時まで) |
| 観 覧 料 | 一般300円(団体20名様以上は一人200円)、中高生100円 |
| 休 館 日 | 日曜日・月曜日(祝日開館・翌火曜休館)・第4木曜日(7月24日、8月28日) |
| 編集委員 | 須田喜代次・紅野謙介 |
開催にあたって
日本近代文学館では、国語教育の現場と文学研究の成果を館が橋渡しする形の企画展「教科書のなかの文学/教室のそとの文学」を2017年度から開催しています。今回取り上げる作品は、森鷗外「舞姫」ですが、2019年度に開催された同名企画展の再開催となります。
「舞姫」は、1890(明治23)年1月、鷗外最初の創作小説として雑誌『国民之友』に発表された作品です。2025年現在発表から130年以上もの時間が経過したことになります。その「舞姫」が初めて高等学校国語科教材となるのは、1957(昭和32)年のことでした。高校生にとって、必ずしも読みやすい文体とは言えないにも関わらず、以後高校国語科定番教材としての位置を保ち続けて、およそ70年に及ばんとしています。では、その「舞姫」が〈今、ここ〉に生きる私たち(特に若い世代の人たち)に問いかけてくるものは何なのでしょうか。
本展覧会では、第1部において「舞姫」という作品世界にしっかり向き合うために、現存する「舞姫」草稿の問題、発表当初からの作品享受のありよう、主人公太田豊太郎が生きた時間、彼が歩いたベルリンという空間、そして近年判明したエリスのモデルであるElise Wiegertのことなど様々な角度から光線を当てることを目指します。そして第2部では、同時代あるいは後につづいた作家たちと、鷗外/鷗外作品との交響の様を追います。
(編集委員 須田喜代次)
第1部 「舞姫」の世界
Ⅰ.「舞姫」―〈今、ここ〉に問いかけるもの
近代小説を切り拓いた作品「舞姫」。その世界と従来の読みを紹介すると共に、今を生きる私たちが「舞姫」を読む意義について考えます。
Ⅱ.「舞姫」登場とその評価
「舞姫」は清新な文体とセンセーショナルな内容により、大きな反響をもって迎えられました。同時代評をはじめ、掲載誌などの書誌資料から、発表当時の「舞姫」の姿を紹介します。
Ⅲ.ベルリンという空間
「舞姫」はベルリンという都市空間を描いた最初の都市小説でもありました。「舞姫」に描かれたベルリンの姿を、当時の写真資料や、同時代の日本人の訪問記などと共に展観します。
Ⅳ.留学・恋愛・国家
鷗外は1884年、陸軍軍医としてドイツに留学、その体験をもとに「舞姫」を描きます。近代医学の修得という国家の命運を背負っての留学でした。書簡や日記など滞独中の資料を中心に、留学時の鷗外の姿に迫ります。
Ⅴ.広がる「舞姫」の世界
「舞姫」は、昭和30年代から現在に至るまで、多くの国語教科書に採用されつづけています。教材としての「舞姫」をどのように読むか、その作品鑑賞の楽しみ方、魅力に迫ります。また、映画・劇・漫画・小説など、新たな姿に生まれ変わった「舞姫」の世界を紹介します。
第2部 文学者たちとの交響
Ⅰ.鷗外の同時代人
若き日の鷗外に影響を与えた西周や徳富蘇峰、日本の近代文学の出発期をともに支えた坪内逍遥、二葉亭四迷などについて紹介します。
Ⅱ.鷗外周辺に集まった人々
鷗外は歌人・詩人としてもすぐれ、その周辺には多くの文学者たちが集まりました。常磐会や観潮楼歌会での鷗外と歌人たちとの交流、また、『スバル』や『三田文学』などの作家たちについて展観します。
Ⅲ.鷗外との共振
戦時下に鷗外を論じた中野重治や石川淳から、近年鷗外を甦らせた伊藤比呂美まで。鷗外没後にその作品を読み直し、自らの文学を生み出す源泉とした作家たちについて紹介します。
Ⅳ.鷗外の子供たち
鷗外は五人の子供を持つ父親でもありました。個性豊かな子供たちが書き残したものを手掛かりに、父親としての鷗外の側面に迫ります。